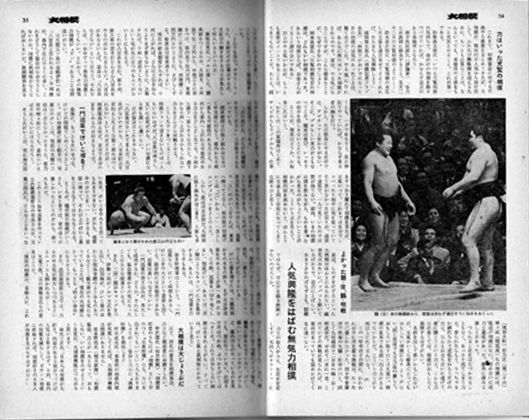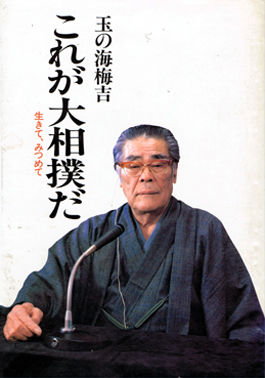専門誌「大相撲」が不人気を脱し、興隆を
迎えるためには、本場所の土俵をもっと充実
させることであることが第一である、と記述
している。現代の理事長も土俵の充実をスロ
ーガンにしている。大相撲を面白くする方法
は内容のある相撲といえる。
昭和天皇は相撲好きであり、しばし天覧相撲
がおこなわれていた。その日の相撲は白熱し、
活気に満ちていたと、評論家やメディアは
発言している。常に天覧相撲のような精神で
取れればいいのだが、そうはいかない現状が
あった。「大相撲」は指摘する。ただ、懸命
やるだけでは、アマチュアと変わりがない。
そこに、プロらしい実力がともなってこそ、
観客は喜び、いっそうの拍手を惜しまない
ことになる。
そして手に汗をにぎる熱戦が少ない原因を
こう分析している。まず、力士の収入が安定
して力士のサラリーマン化につながっている
ことをあげている。そのためにも枚数ごとに
月給に差をつけろと提言している。そうで
ないと上がることより現状を守ろうとする。
しかし、枚数ごとに月給に差をつける制度は
未だに実現していない。
また無気力相撲という名の八百長と思われる
相撲が横行しており、これでは熱戦からほど
遠くなる、とも述べている。そのためにも、
同系統の取組は中日前に実施し、後半は幕内
下位対十両上位、十両下位対幕下上位の対戦
をどんどん増やすことである。ただ、協会は、
八百長がない建て前であるだけに、前記の
ようなことはおこなわれるはずがなかった。
これでは土俵の充実は遠ざかる一方になる。
ちなみに現代は八百長的行為をおこなわない
よう各力士に誓約書を提出させている。
内容ある相撲の裏づけとなるのが、稽古で
ある。大合併の巡業ではどうしても稽古量に
限界がでてくる。6場所制がそのままで稽古
量を増やすのなら大合併巡業をやめること
が第一条件になる、と「大相撲」は指摘する。
そのかわり、一門巡業、あるいはキャンプ、
部屋稽古にすべきと主張している。大合併の
巡業は現代も変わらない仕組みである。
厳しい評論でなる天竜・玉の海両氏は次の
ように意見している。「現在の相撲は、見物
人に、これはという興奮を与えていない。
攻めて攻め返す相撲の醍醐味を、観衆に味わ
わせていない。けいこ場へ行っても、シコや
テッポウなど、幕内力士のやっているのを
見ても型になっていない。仕切りで手はつか
ぬ、ぶつかりけいこはへたくそ。これでは
おもしろい相撲は生まれようがない。すべて
はけいこ量と真剣味にかかっていると思う」
と厳しい。両氏が現代の吊り出しとうっちゃ
りがほとんど消失した相撲を見たら果たして
何と言うか。土俵の充実は容易なことでは
ないことがわかる。
(この項目終わり)
逆説の日本史を読んでいます。
興味深いテーマをこれからもお届けします。
マーク2カ所をクリックして支援して
ください。
ください。
よしなに
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
↑↑↑↑↑↑↑↑