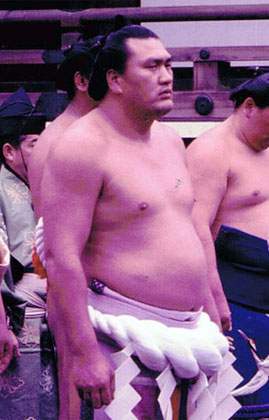現代の大相撲は重量級時代である。では大相撲重量級時代は横綱の
代でいうと誰から始まったのか。そこで歴代横綱の体重を調査して
みた。そこから読み解くと隆の里からである。隆の里は159キロで
あった。ただし、隆の里自身は127キロの千代の富士との優勝争い
が目立った。

隆の里以降の横綱の体重は以下である。
双羽黒 157キロ
北勝海 151キロ
大乃国 203キロ
旭富士 143キロ
曙 235キロ
貴乃花 160キロ
3若乃花134キロ
武蔵丸 237キロ
朝青龍 148キロ
白鵬 154キロ
日馬富士133キロ
鶴竜 155キロ
稀勢の里171キロ
照ノ富士178キロ
200キロ越えが大乃国、曙、武蔵丸と3人もいる。130キロ代は3代
目若乃花と日馬富士の2人だけである。貴乃花は曙の強烈な突き押
しに対抗するために体重を増加させた。入門時60キロ台だった白鵬
が154キロになるのだから驚きである。

東京相撲の明治・大正時代はどうだったのか。横綱が地位化した常
陸山以降をみていく。
常陸山 148キロ
2梅ヶ谷158キロ
太刀山 139キロ
鳳 113キロ
2西ノ海139キロ
大錦 141キロ
栃木山 103キロ
宮城山 113キロ
3西ノ海116キロ
常ノ花 113キロ
明治・大正の東京横綱の平均体重は127.1キロである。常陸山・2
代目梅ヶ谷・大錦は大型に入る。常陸山は相手の攻めを受けてきた
が、大型なればこそ可能だった。栃木山は小兵に見えるがまわりに
特に体重のある力士はいなかった。

昭和戦前は以下である。
玉錦 139キロ
武蔵山 116キロ
男女ノ川146キロ
双葉山 128キロ
羽黒山 129キロ
安藝ノ海128キロ
照國 161キロ
照國が特出している。そして男女ノ川が続いている。昭和戦前の入
幕力士の35%以上が100キロ未満であった。双葉山は体重が少ない
時期はうっちゃり双葉といわれた。体重の増加とともに寄り、上手
投げを繰り出した。

昭和戦後は次である。
前田山 116キロ
東富士 176キロ
千代の山123キロ
鏡里 161キロ
吉葉山 143キロ
栃錦 131キロ
1若乃花108キロ
朝潮 135キロ
大鵬 153キロ
柏戸 139キロ
栃ノ海 110キロ
栃錦は最終的に131キロではず押しの相撲を取った。入幕の頃は86
キロで動き回って多彩な技の相撲で勝機を見いだした。また驚異の
粘り相撲でマムシと呼ばれた。初代若乃花の体重は大きく変化しな
かったが、鬼気迫る相撲を取って土俵の鬼と言われた。栃ノ海は軽
量に泣いた。

部屋別総あたり以降が以下である。
佐田の山129キロ
北の富士135キロ
玉の海 134キロ
琴櫻 150キロ
輪島 132キロ
北の湖 169キロ
2若乃花123キロ
三重ノ海135キロ
千代の富士127キロ
昭和59年の幕内平均体重は129キロであった。千代の富士は小さい印
象があるが、それでも120キロ以上あった。北の富士・玉の海のころ
は130キロ台で、150キロあったら巨漢だった。巨漢の代表は高見山
であった。時代は移って北の湖が巨体をぶつける相撲を取った。輪
島は体重差のある北の湖相手によく対抗したものである。輪島はや
はり天才であった。